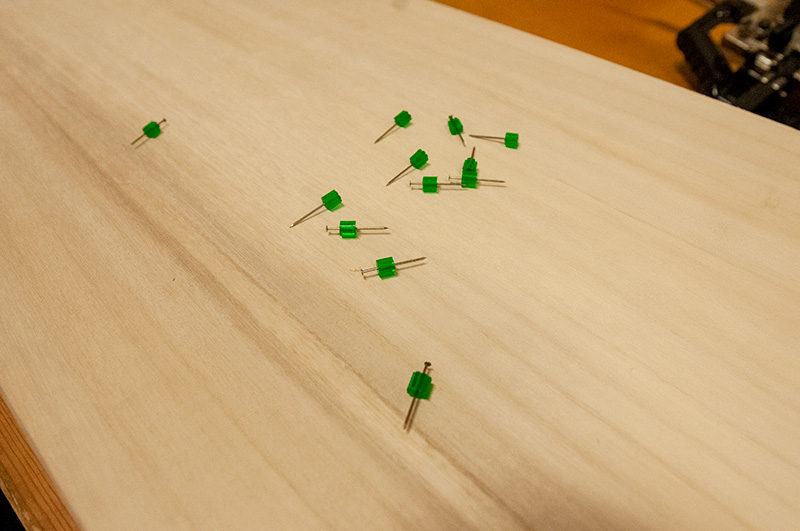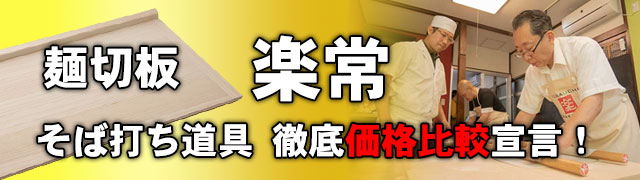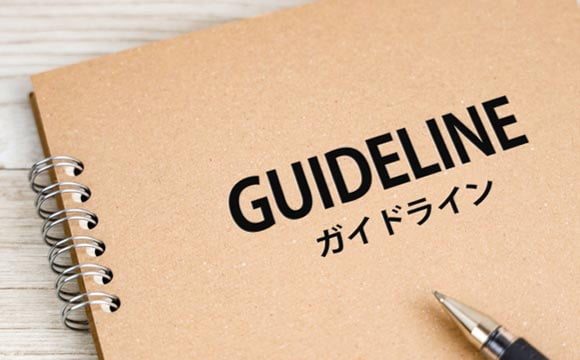今回のDIY講座はまな板。
麺切り板・蕎麦切り板などとも呼ばれたりしているが、要はただの板で結構。
作り方と言っても、本当にただ板を切るだけの作業であり、特にレクチャーするまでもないのだが、厚みや素材の良し悪しもあるので、その辺りを重視して解説してみたいと思う。
まずはホームセンターで材料探しをしてみよう。
ホームセンターで材料探し
ホームセンターに行くと様々な木材が販売されているが、まな板として重要なのは、反りにくい木材を使用するということである。
延して畳んだ蕎麦の麺体を置くことになるので、多少の水分がまな板に付着することになる。
木材であるがゆえに、その水分を吸ってしまうと、その水分が乾く時に反りに影響する。
この反りは木の裏表によって反り方が決まっている。

簡単に言うと無垢材という一本の木から製材されている板を使うのは反りに繋がるので、接着剤が使用されているとは言え、やはり集成材を使うのがベストだと思っている。
一番適しているのは、ヒノキの集成材だがなかなか目の良いヤツに巡り合わないし、そもそも楽常では出張そば打ち道具として軽量化する必要性があるので、桐材を使っている。
洋モノの材料に、ホームセンターでもよく目にするファルカタ材でも代用が効く。

ただし、軽い材料だが、反りには比較的弱いので、ご家庭で使う場合にはパインの集成材などがリーズナブルで手に入れやすいのではないかと思う。
道具を揃える
さて、材料を揃えたら、今回必要な道具を紹介しよう。
これまでの麺台の作り方などでもレクチャーしたが、電動工具は必須である。
手ノコでギコギコとやっても真っ直ぐに切れない。
もちろん苦労してやってもいいのだが、その後切り口を真っ直ぐに整えるには、カンナを使ったりしないとならず、新たな道具が必要となってしまう。
てっとり早いのは、レンタル工具である。

こちらのホームセンターではモノによるが、1泊2日で¥300~借りれるシステムだ。
また、そもそも切ったりするのに面白みを感じない方は、カットサービスなどを利用するのも◯だ。

製材するのに、カットする寸法などは市販のモノを参考にすると良いであろう。
道具を自分で使って自分で作り上げる愉しみを得る場合は、次のステップに進んで頂きたい。
道具一式
と、まあ、ただ木板を切るだけなのでこんなもんで大丈夫です。
ただし、板をまっすぐに直角に切るという作業は、言うほどたやくすはないので、順を追ってレクチャーしてみよう。
製作開始
長方形にカットする
まな板が完成!
最終的にすべての面をペーパーあてを行い、とげが刺さらないようにしておこう。
材料の厚みに触れなかったが、正直、これはコストの問題である。
厚みが増せばその分材料費が上がるし、薄ければ安く済む。
真っ直ぐな材料であれば、5mmや4mmのベニヤ板でも構わないし、そもそも目的を考えれば、麺台が傷つかないようにするだけの道具である。
まして打ち粉を振ってから麺体を乗せるわけですから、樹脂でもぜんぜん構いません。
確実に言えるのは、市販されているようなムダに分厚いまな板は、まったくもって無意味と言えます。
高いお金を出して購入する必要性はまったく考えられない道具のひとつと言えるでしょう。