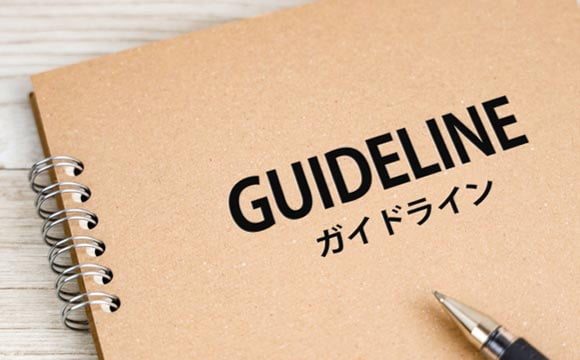そば打ちを仕事としていると、もちろん、お客様から聞かれることもありますし、自分自身でも、どうして、あの白くて美しい花を食べようと思ったのか?
と不思議になることもあります。
蕎麦に携わる仕事をしているということもあり、今回は、しっかりと蕎麦のルーツについて調べてみたので、皆さんと情報を共有し、そうした背景を踏まえ、そば打ちをもっと楽しんでみるのもイイのではないかと思っております。
蕎麦のルーツ
蕎麦の歴史は古く、原料としては高知県にある遺跡から蕎麦の実の花粉が発見されて、9000年以上前のものと調査の結果で分かり、昔から馴染みが深い植物、食べ物であったことが分かります。
史実を紐解くと、蕎麦が食べ物として用いられるようになったのは奈良時代以前となりますが、当時は今のように麺としてではなく、粒のまま粥にして食べていました。
[wp-svg-icons icon=”point-right” wrap=”i”] wikipedia 奈良時代
奈良時代イメージ と そばがゆ
またこの時期に蕎麦の栽培がはじまったことが書籍から分かり、平安時代には和歌として詠まれています。
[wp-svg-icons icon=”point-right” wrap=”i”] wikipedia 平安時代
ただ美味しさではなく、飢饉などに備えてのものでした。
蕎麦は飢えを凌ぐ非常食?
食べ方としては粥の他に粉にして、練って作る蕎麦がき、水で溶いて焼いた蕎麦焼きとして食べられるようになり、小麦粉の代用として使われるようになりました。
しかしまだ美味しさという意味ではほど遠く、飢えをしのぐためといった目的が主流となり、富裕層や貴族社会ではほとんど食べられてはいませんでした。
こうした飢えを凌ぐ目的というところがピンと来ないという方もおられるのではないかと思いますが、これにはしっかりとした理由があるのです。
お米や小麦粉に比べ、蕎麦は荒れた地でも育ち、かつ、種蒔き後、4~5日で発芽し、30~35日目頃に開化最盛期を迎え、70~80日で収穫適期となるため、格段に早く、年に2回は確実に、いや、うまくすれば3回収穫できるスピードフードであったのだ。
参考:新・日本風土記『蕎麦』から
この収穫スピードの理由により、蕎麦は、その後に起こる戦争による貧しさもあった昭和初期の時代も、農家さんらに、飢えを凌ぐ 主食 兼 非常食 として食べ続けられることになったのだ。
ある意味、日本の風土にあったスーパーフードということですね。
蕎麦が麺になった時代
現在の形状に近付いたのは江戸時代で、この頃に蕎麦を麺として食べるようになり、蕎麦がきと区別するために「蕎麦切り」と呼ばれていました。
[wp-svg-icons icon=”point-right” wrap=”i”] wikipedia 江戸時代
現在一般的に使用されている「蕎麦」という呼び方は蕎麦切りが省略されたものであり、地方によっては「蕎麦切り」の呼称が残っています。
ただ江戸時代の蕎麦は現在のように茹でるのではなく、蒸す調理法を取っていました。

理由としてはつなぎを使わない十割蕎麦は切れやすいので、切った蕎麦を蒸籠に乗せて蒸し、そのまま客に提供する形が主流でした。
今でも「盛り蕎麦」を「せいろ蕎麦」と呼ぶのはこの名残です。そして十割蕎麦の一方で小麦粉のつなぎを加えた二八蕎麦も誕生して、こちらは蕎麦粉が8で小麦粉が2の割合で打たれた蕎麦のことを言います。
これには諸説あり、名称に関しては蕎麦粉と小麦粉の割合から、または値段が16文であったことから、2×8=16の符丁からきたものという説があります。
蕎麦としての形状は整いつつありますが、驚くのはそばつゆで、この時代は今のような鰹節の出汁に醤油や味醂が加えられたものではなく、味噌がベースとして使われていました。
シンプルに「味噌だれ」と呼ばれていて、味噌に水を加えて煮詰め、布袋に入れて吊るし、垂れてきた液体を利用していました。

「たれみそ」と呼ばれて、江戸時代初期の料理本には、たれみそに大根の汁、削り節、大根おろし、あさつきを入れて、芥子や山葵を加えても良いとあります。現在陣のイメージするそばつゆとは違いますが、こちらが主流でした。
また蕎麦といえば江戸っ子の食べ物という認識が強くありますが、江戸の初期では実は蕎麦よりも、うどんの方が人気がありました。
上方から伝わったうどんと薄口醤油のコンビネーションは、またたく間に江戸の街に広がり、ブームを築くことになったのですが、江戸本来の食べ物を求める声も少なくなく、蕎麦を江戸のソウルフードにする!という仕掛け人が居たとも言われています。
うどんのように重たい主食とは違う提供方式で、お三時につまむようなファーストフード的になった蕎麦は、つゆにいたっても、どこまでも上方に対抗すべく、濃口しょうゆに変えられたほどです。
江戸のソウルフード「蕎麦と酒」の誕生
蕎麦の人気が高まってきたのは18世紀中ごろで、中期から後期にかけてです。
この頃になると江戸にそば屋は数えきれないほどあり、逆にうどん屋の数は激減してきました。
理由としては二八蕎麦の誕生により、蒸すから茹でる調理法がとられるようになって、本来の美味しさを味わうことができるようになったからです。
また蕎麦に人気を高めようと店側もさまざまな工夫を凝らして、今もそば屋で酒を飲むのが粋と言われているのは、蕎麦が茹で上がるまでの時間を短気な江戸っ子に楽しく過ごしてもらいたいと思い、酒を供するようになりました。
ただ蕎麦と酒というのは必ずしも相性が良い組み合わせではないと思われており、そのため酒を楽しむ人のために蕎麦を抜いた「ぬき」、蒲鉾を薄く切ってわさびと醤油を添えた「板わさ」、天ぷらの「天たね」などのメニューがありました。
いわゆるおつまみですが、どれもそば屋に常備されている食材であり、つまみとして用意しているものではないのがポイントです。
昼間でも軽く酒が飲みたい時にそば屋に行けば、特に文句を言われることなく楽しめるので、そういった意味でも人気が爆発的に高まっていきました。
これが、今、巷で人気の「蕎麦屋呑み」のルーツと言ってイイでしょう。
江戸の三大蕎麦
そして爆発的に増えた店の中でも、現在まで続く老舗がありました。
「老舗御三家」や「江戸の三大蕎麦」で、「藪(やぶ)」「更科(さらしな)」「砂場(すなば)」という屋号が系譜になります。



そば屋ののれんを見るとこれらの名前が書いてあることが多く、数えきれないほどあった店の中で選ばれているだけに美味しさは格別です。
ご当地蕎麦
また蕎麦は地域性が高い食べ物で、長い歴史の中でさまざまに変化してきています。
地域特産の食材をのせる「にしんそば」や「はらこそば」「しっぽくそば」などがあり、調べてみると蕎麦だけではなく土地の歴史も見えてきます。
にしん蕎麦
はらこ蕎麦
しっぽく蕎麦
飢饉に備えて植えられた一面もあり、緊急時の代用品として食べられてきたものが、今は世界に誇る日本の名物料理となっています。
江戸時代に「蕎麦切り」として完成しましたが、今も新しい可能性を求めてチャレンジが続けられて、自由なコンセプトで新メニューが作られています。
中でも、斬新だったのであろう蕎麦メニューが、南蛮渡来であったカレー粉とだし汁を合わせた、カレー南蛮だ。
カレー南蛮そば
もはや、蕎麦屋の定番メニューとなっているのは、蛋白な蕎麦に、ガツン!と効いたスパイスで、少しとろみを付け、主食としても満足の行く蕎麦メニューとなったのは、当時は衝撃のメニューだったであろうと思う。
蕎麦は昔ながらの伝統的な食べ物ですが、それだけに古臭いイメージが強いのが難点です。
変わらないことも大切だが、それ以上に、今の時代に合わせた蕎麦を提供するというのは、もっと難しく、世相に受け入れて貰うまでには、長年に渡っての味の追求が、定番メニューになり得る基盤となるのであろう。
そこで若い女性が好むおしゃれ感のある蕎麦が作られるようになって、そこから美味しさを知ってもらい、伝統も守るサイクルが生まれています。
ラー油蕎麦
トマト蕎麦
バジル蕎麦
昨今では、蕎麦屋も二極化してきており、昔ながらのスタイルを貫き通す蕎麦屋、対して、前述のとおり、若い人にも蕎麦を楽しんで貰うために入り口を広げるスタイルの蕎麦屋に分かれて来ている。
その中でも、新たな味の定番を狙って、思い思いの蕎麦屋スタイルを考え、求めるのはお客様への満足という信念を持って営んでいる蕎麦屋さんの数々を、ご自分のライフスタイルで、美味しく味わって頂ければと思います。
百あれば、百の蕎麦の味がある。
それが、SOBAUCHI楽常の追い求める、これからの蕎麦スタイルです。